11月銕仙会定期公演にて清水寛二がシテをつとめます、能『仏原』をより楽しんでいただくため、
曲目研究会を開催します。
■日時 10月30日(木) 18:30より2時間程度を予定
■会場 銕仙会能楽研修所 (東京都港区南青山4-21-29) 地下鉄「表参道」駅下車A4出口
■参加費 11月定期公演チケットをご購入いただいている方は無料です。
研究会のみの方は500円を当日ご用意ください。
■お申込み・お問い合わせ TEL 03‐3401‐2285 (銕仙会事務所・平日10時~17時)
※事前にご連絡をいただけますと幸いです。お気軽にお越しください。
公演のチケットも電話にて受け付けています。
■講師
表きよし:国士舘大学21世紀アジア学部教授
オフィスしみかん「世阿弥の伝書を読む」講座講師・銕仙会公開講座講師
石丸晶子:東京経済大学名誉教授
著書に『式子内親王-面影びとは法然』・短編小説集『月影の使者』など
■主催 清水寛二・オフィスしみかん
■協力 銕仙会 http://www.tessen.org
曲目研究会を開催します。
■日時 10月30日(木) 18:30より2時間程度を予定
■会場 銕仙会能楽研修所 (東京都港区南青山4-21-29) 地下鉄「表参道」駅下車A4出口
■参加費 11月定期公演チケットをご購入いただいている方は無料です。
研究会のみの方は500円を当日ご用意ください。
■お申込み・お問い合わせ TEL 03‐3401‐2285 (銕仙会事務所・平日10時~17時)
※事前にご連絡をいただけますと幸いです。お気軽にお越しください。
公演のチケットも電話にて受け付けています。
■講師
表きよし:国士舘大学21世紀アジア学部教授
オフィスしみかん「世阿弥の伝書を読む」講座講師・銕仙会公開講座講師
石丸晶子:東京経済大学名誉教授
著書に『式子内親王-面影びとは法然』・短編小説集『月影の使者』など
■主催 清水寛二・オフィスしみかん
■協力 銕仙会 http://www.tessen.org
来たる11月14日の銕仙会定期公演にて清水寛二がシテをつとめます『仏原』。
秋深い加賀の国、仏の原を舞台として、平清盛に愛された白拍子仏御前の霊が旅僧の前に現れ、妓王・妓女とのことなどを語り、しっとりとした舞を舞います。
「能の本を書くこと、この道の命なり」(花伝第六花修云)と書いた世阿弥ですが、『三道』〔能作書条々〕には、能の本説について、「女体には、伊勢・小町・祇王・妓女・静・百万、如此遊女、是はみな、其人体何れも舞歌遊風の名望の人なれば、これらを能の根本体に作りなしたらんは、をのずから遊学の見風の大切あるべし。」と記しています。
『仏原』もなかなかよい曲だと言われていますが、残念ながらあまり上演されません。今回の上演の機会に、「世阿弥の伝書を読む」シリーズ講座で講師をお勤めいただいた表きよし先生と、この『仏原』の本文を読み、典拠や作者、演出などをさぐってみたいと思います。
また、ゲストとして石丸晶子先生をお招きし、仏御前のことについて、加賀の国に帰ってからの地元に伝わる伝説などをお話しいただきます。偶然なことに石丸先生には清水が高校時代古文の授業で源氏物語などを教わりました。
秋の佳曲『仏原』をぜひご覧頂きたく存じます。そして、演者と研究者の二つの視点から作品をさぐるこの機会、もしご興味がおありでしたらどうぞご参加ください。
―銕仙会定期公演11月公演―
*11月14日(金)18:00開演 水道橋・宝生能楽堂にて
能『仏原』清水寛二・狂言『右近左近』山本泰太郎・能『車僧』小早川修
秋深い加賀の国、仏の原を舞台として、平清盛に愛された白拍子仏御前の霊が旅僧の前に現れ、妓王・妓女とのことなどを語り、しっとりとした舞を舞います。
「能の本を書くこと、この道の命なり」(花伝第六花修云)と書いた世阿弥ですが、『三道』〔能作書条々〕には、能の本説について、「女体には、伊勢・小町・祇王・妓女・静・百万、如此遊女、是はみな、其人体何れも舞歌遊風の名望の人なれば、これらを能の根本体に作りなしたらんは、をのずから遊学の見風の大切あるべし。」と記しています。
『仏原』もなかなかよい曲だと言われていますが、残念ながらあまり上演されません。今回の上演の機会に、「世阿弥の伝書を読む」シリーズ講座で講師をお勤めいただいた表きよし先生と、この『仏原』の本文を読み、典拠や作者、演出などをさぐってみたいと思います。
また、ゲストとして石丸晶子先生をお招きし、仏御前のことについて、加賀の国に帰ってからの地元に伝わる伝説などをお話しいただきます。偶然なことに石丸先生には清水が高校時代古文の授業で源氏物語などを教わりました。
秋の佳曲『仏原』をぜひご覧頂きたく存じます。そして、演者と研究者の二つの視点から作品をさぐるこの機会、もしご興味がおありでしたらどうぞご参加ください。
―銕仙会定期公演11月公演―
*11月14日(金)18:00開演 水道橋・宝生能楽堂にて
能『仏原』清水寛二・狂言『右近左近』山本泰太郎・能『車僧』小早川修
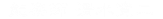
 RSS Feed
RSS Feed
